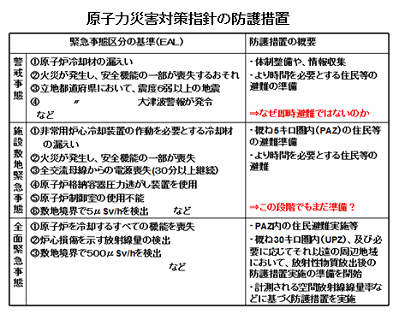HOME > 原子力防災
自治研かごしま 2014年6月号掲載記事に加筆修正
机上の防災・避難計画では住民の安全は守れない
問われているのは原発再稼働の是か非かではない。鹿児島県や薩摩川内市などに、住民の生命財産を守るという自治体の最も基本的な責務を果たす意思があり、その能力があるかどうかである。
事故を前提とした再稼働
原子力規制委員会が新規制基準への適合審査を進めている。昨年7月に申請された九州電力など加圧水型6原発12炉に加え、その後東京電力柏崎刈羽原発を含む沸騰水型6原発7炉も申請が出された(6月末現在)。審査が長期化することへの批判があることから、原子力規制委員会は3月に川内原発を優先審査することを決定し、審査を加速、先日基準に適合するとの審査書案をまとめた。
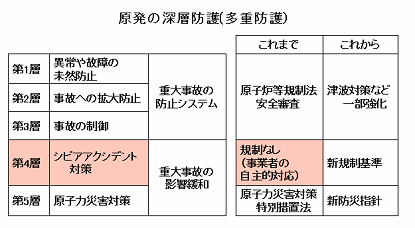 優先審査決定を受けて記者会見した岩切秀雄薩摩川内市長は「日本で一番安心安全な原発と理解したい」と述べている。いくら原発再稼働を公約に掲げて当選した市長とはいえ、原発地元で新規制基準と安心安全が別の問題であることを理解していないのでは、失格である。
優先審査決定を受けて記者会見した岩切秀雄薩摩川内市長は「日本で一番安心安全な原発と理解したい」と述べている。いくら原発再稼働を公約に掲げて当選した市長とはいえ、原発地元で新規制基準と安心安全が別の問題であることを理解していないのでは、失格である。
新規制基準は、国際的な多重防護の考え方に対応して作られたものだ。右表に示すように福島事故以前の日本では、シビアアクシデント(過酷事故)は想定不適当とされ、第1層から第3層の対応で済まされてきた。しかし実際に福島第一原発で過酷事故が起こってしまったことから、これまで事業者の自主的な対応に任されていたシビアアクシデント対策として定められたのが新規制基準である。
新規制基準はシビアアクシデントを未然に防止するものではなく、シビアアクシデントが一定の確率で起こることを前提に、その影響をできる限り緩和しようというものでしかない。新規制基準で新たに設置が求められたのが第二制御室やフィルターベントであることからも明らかだ。
新規制基準を満たしても安全ではないことを明確に示すのが、 4月11日に閣議決定されたエネルギー基本計画である。
「原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。」とした計画には、次のような記述がある。
「東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて、そのリスクを最小限にするため、万全の対策を尽くす。その上で、万が一事故が起きた場合には、国は関係法令に基づき、責任をもって対処する。」
「安全神話」が崩壊した今、万が一とはされているものの、リスクはゼロではなく、次の事故を想定せざるを得ないのだ。
福島原発事故の教訓
3年が経過しても約14万人が故郷を追われて避難生活を余儀なくされている福島原発事故。福島県では、避難生活での体調悪化やストレスが引き金になった自殺などの震災関連死が本年3月末で1704人にのぼり、地震や津波の直接死者数1607人を既に上回っている。
事故直後の避難行動で大きな犠牲を出したのが大熊町の双葉病院だ。自治体に住民の命を守る能力があるか検証するために、双葉病院の避難がどのように行われたか、振り返っておこう。
事故当時、同病院には338人が入院し、うち146人は寝たきりや病状が重い患者だった。事故翌日の午前5時44分、10キロ圏に避難指示が出され、原発から4.5キロに位置する同病院も朝7時ごろから歩ける患者を数百メートル離れた町役場まで2度連れて行った。しかしそこでは避難バスを待つ長蛇の列ができており、寒風の中、長時間待つことなどできず、病院へ引き返さざるを得なかった。
病院職員は町の災害対策本部で、朝8時ごろに直接、渡辺利綱大熊町長に病院に避難バスを差し向けるよう要請している。その結果、その日の午後になって大型バス5台が来たが、寝たきりの患者は乗ることができない。129人の患者が残され、全員乗れないと町長にも伝えられたが、大熊町は役場ごと先に避難してしまった。なぜ救出を徹底しなかったのかと問われた町長は「あとは自衛隊に任せたというほかありません。町としてはどうしようもできなかった。」とインタビューに答えている。
最終的に自衛隊が最後の患者を救出したのは、地震から5日後であった。それまでの間、院長は少ないスタッフで悪戦苦闘を強いられる。連絡要員として病院にいた自衛隊輸送支援隊長が、原発の爆発音を聞いて、病院職員から車を借りて逃走するという事件もあった。救出が遅れ、近くの避難所が満杯のため250キロ弱の長距離避難となった患者さんから50人の死者がでたのである。(以上 森功著「なぜ『院長』は逃亡犯にされたのか」講談社参照)
被曝が避けられない原子力災害対策指針
双葉病院のような悲劇を繰り返さないため、原子力防災体制は改善されたであろうか。答えは否である。
原子力規制委員会が新たに定めた原子力災害対策指針では、防災計画を定める範囲がおおむね30キロ圏に拡大されるとともに、避難等の防護措置を発動する判断基準に新しい概念が導入された。
概ね半径5キロ圏のPAZでは、あらかじめ決めた緊急事態を区分するための判断基準EALで自動的に防護措置を実施するとされている。EALで警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急事態のいずれに該当するかが決まれば、防護措置、すなわち避難するかどうかが決まる仕組みだ。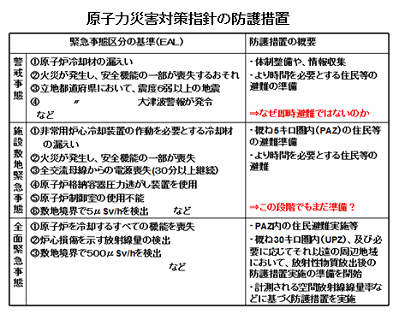
ところが、原子力規制委員会が定めた判断基準EALと防護措置の表を見ると、信じられないものであった。冷却材の漏えいや震度6弱以上の地震は警戒事態に区分されるが、この段階では体制整備や情報収集とされ、即時避難ではない。電源喪失の継続や格納容器圧力逃し装置いわゆるベントの使用は施設敷地緊急事態に区分されるが、この段階でもまだ避難の準備とされている。避難指示が出るのは炉心損傷が始まった全面緊急事態になってからというのだ。
また、概ね30キロ圏とされる緊急時防護措置を準備する区域UPZでは、環境における計測可能な判断基準OILを用いるとされている。放射能が放出され、放射線量が上がれば迷うことなく避難を判断できるだろうというのだ。つまりこの区域では予防的な措置は完全に断念され、放射線レベルが上がらないと避難の指示が出ない。
判断基準OILにはいくつかの種類が用意され、緊急に避難するOIL1は、毎時500マイクロシーベルトとされている。この値は平常時の約1万倍に相当し、避難しないで留まれば1週間で50ミリシーベルトの被曝に相当する。また、OIL2で毎時20マイクロシーベルトが検出されると1週間程度のうちに一時移転の指示が出ることになっている。いずれにしても線量が上がらないと指示が出ないのだから、避難中の被曝は避けられない。
ところが、鹿児島県や薩摩川内市、いちき串木野市などは、問題のある指針に忠実に従って防災計画の改定を行っている。
屋外に集合する避難などあり得ない
さらに問題なのは、具体的な避難方法を定めるべき避難計画が、全くの机上の作文に過ぎないことだ。
鹿児島県の防災計画では「避難の際は、原則、自家用車両を利用するものとし、自家用車両による避難が困難な住民については、近所の方との乗り合い、若しくは、集合場所に参集し薩摩川内市、関係周辺市町等の準備した車両により避難を行う。」と書かれている。
一方、薩摩川内市やいちき串木野市などの広域避難計画を見ると、自治会ごとに人口、世帯数、バス避難集合場所、避難経路、避難先施設が一覧表になっているだけ。自家用車両による避難が困難な住民が何人いるのか。そのために必要なバスは何台か。また、そのバスをどのように調達するのか何も書かれていない。民間人であるバス運転手の被曝防護ができなければ避難計画は成立しないはずだ。
確保できる台数に限りがあるためバスはピストン輸送になると考えられ、避難先が遠方になれば次のバスがやってくるまで長時間待たなければならない。双葉病院の例を見ればわかるように、仮に放射能が飛んできていなくても、自家用車を使えない避難弱者は高齢者であったり病気などのハンディーを持っていたりすることが多いと考えられ、屋外で長時間避難を待つことなどできない。
ところが、薩摩川内市の避難計画では、原発から約3キロ、PAZ圏内の倉浦自治会はバス停前が集合場所とされている。いちき串木野市の避難計画でもバス停や公園、グラウンド、橋、郵便局前などが集合場所に指定されている自治会が約3割もあった。同市は5月末に計画を改定したが、なおバス停が集合場所の自治会が複数残っている。姶良市は1集落のみがUPZ圏内とされているが、その集合場所も交差点とされている。いずれも大勢が集まれる公民館などが集落の近くにないからであろう。
昨年10月11日、12日の両日、川内原発で行われた国主催の原子力防災訓練の監視行動に参加させていただいたところ、通常時の約400倍の高線量が検出されている想定にもかかわらず、訓練参加者がバス停で避難バスを待っていたのに驚いたが、訓練の想定の問題ではなく、避難計画そのものにバス停集合とされているのだから、論外である。
繰り返しになるが、PAZ圏内の薩摩川内市倉浦自治会に避難命令が出るのは、炉心溶融が始まり大量の放射能が放出されている時である。またUPZ圏内のいちき串木野市や姶良市に避難命令が出るのは、平常時の1万倍の放射線が検出されている時である。このような時に、いつ来るかわからないバスを屋外で待って、その間被曝し続けることが前提では避難計画とは言えない。
避難経路は複合災害時に利用可能か
倉浦自治会の集合場所とされているバス停は川内川河畔の国道43号線にある。地震によって原発事故となった場合、川内川を津波が遡り、この場所にそもそも集合できないことも考えられる。現に避難計画では、PAZ圏内の滄浪地区は国道43号線を利用するルートと河口大橋を利用して迂回するルートの2つが示されている。倉浦自治会の代替ルートも原発に近づく方向の河口大橋経由となっているが、問題は河口大橋へ行くまでの国道43号線であり、代替ルート足りえない。倉浦自治会に限らず、30キロ圏外の避難場所までのルートでも崩落等による通行不能場所が生じないという保証はない。
また、甑島も一部がUPZ圏内となるが、薩摩川内市の防災計画では「OILに基づく防護措置を実施するため、全島民の島外避難に備え、利用可能な船舶の把握のほか、配船計画の検討を行うものとする。」とされている。防災計画では本来「検討を行う」と書くのではなく、その検討した結果にもとづく対策を示すべきだが、いくら検討しても海が荒れたら避難は不可能だ。
避難弱者への配慮は?
薩摩川内市の防災計画には「避難計画(広域避難計画を含む。)を作成する際は、放射線の影響を受けやすい乳幼児等に配慮した計画とする。」と書かれているが、実際には何の配慮も読み取れない。
内閣府大臣官房原子力災害対策担当室長と消防庁特殊災害室長の連名で出されている「地域防災計画(原子力災害対策編)作成マニュアル」では、「病院等医療機関の管理者は、県、所在市町村及び関係周辺市町村と連携し、原子力災害時における避難経路、誘導責任者、誘導方法、患者の移送に必要な資機材の確保、避難時における医療の維持方法等についての避難計画を作成するものとする。」とされ、病院や社会福祉施設の管理者に計画策定が丸投げにされている問題もある。
双葉病院の教訓で明らかなように、救急車や介護タクシー、福祉車両など安全な移動手段を確保し、設備の整った受入施設まで迅速に避難することは容易ではない。30キロ圏外の病院等もたいてい満床状態であろう。心の病や認知症の場合、徘徊や奇声を発することもあり、体育館等で一般の方と一緒に避難生活を送ることは困難だ。口からものを食べられない患者さん用の経管栄養剤、水分が気道に侵入しないようにするとろみ剤、オムツ、褥瘡防止用マットなど医療・介護用品の備蓄や確保も課題だ。
川内原発の場合、避難計画作成が完了している病院・福祉施設は5キロ圏内の7施設にとどまり、10キロ圏10施設が7月中の策定にこぎつけると言う。川内原発の30キロ
UPZ圏内に240の病院・福祉施設があり、患者、入所者は1万4千人にのぼると指摘されているが、伊藤鹿児島県知事は、「10キロまでの計画は作るが、30キロまでの避難計画は現実的でなく、作っても機能しない」と述べている。
さらに、伊藤知事は、「諸外国のUPZというのは、スリーマイル事故のあったアメリカでも15〜16キロ、イギリスはせいぜい5〜6キロ」「UPZは『いざ緊急の時の避難をどうするか?』ですので,広ければ広いというものでもない」「頭の中に30キロは前提としてあるのですが、これさえも動く可能性は、私はあると思う」と原子力災害対策指針さえ否定して、10キロ圏の計画策定で「ほぼ完璧な体制」と強弁するのである。
滋賀県、京都府、兵庫県などが独自に原発事故時の放射能拡散計算を行い、30キロ圏外でも甲状腺被曝線量が国際原子力機関(IAEA)基準の50ミリシーベルトを超えるとして、国に対策を求めているのと比べると雲泥の差である。
避難時間シミュレーションは
それではバスによらない自家用車による避難は可能であろうか。先にも述べたとおり、鹿児島県の防災計画では、原則自家用車利用とされている。
自家用車の避難が中心になれば、渋滞は避けらない。福島事故時には通常約30分で行けるところまで3時間から8時間かかったとの証言もある。また、避難先に十分な駐車スペースがあるかどうかや、放射能検査、除染を短時間で安全に行えるかという問題も解決しなければならない。
原子力規制委員会は、2012年12月12日に「地域防災計画(原子力災害対策編)作成等にあたって考慮すべき事項について」を確認しており、そこでは「移動手段や移動経路に関する事項は、避難時間シミュレーションの結果なども参考にして決定する。」とされている。
実際、旧原子力安全基盤機構(JNES)の支援を受けて各地でシミュレーションが行われている。JNESの資料によれば、標準(日中)、標準(夜間)、悪天候(積雪時)、観光ピーク時期、特別な行事(花火大会)、道路インパクト(津波を想定)、交通規制ありの7つのシナリオでいくつかの条件を変えてシミュレーションが行うとされている。
結果は表のとおり公表されており、鹿児島・川内原発の場合、避難指示後、UPZ圏内の9割の住民が避難し終わるまでに9〜29時間弱かかるとされている。
環境経済研究所の上岡直見氏は「原発避難計画の検証」(合同出版)で独自にシミュレーションを行い、川内の場合、UPZ圏内の避難に高速が使える場合21.5時間、国道のみの場合43時間かかるとしている。
福島原発事故では、地震後43分で原発敷地境界近くにあるモニタリングポストが警報を発しており、津波が来る早い段階から放射能は漏れ出している。新規制基準適合審査に九州電力が提出した資料によれば、川内での最悪事故では炉心溶融開始までわずか19分、原子炉容器からの放射能漏洩まで1時間半とされている。このような短時間では避難が完了しないことを公表されたシミュレーション結果は示している。これでは避難中の大量被曝が避けられない。
渋滞解消策として原子力災害対策指針で打ち出されているのが段階的避難である。段階的避難とは、要するにPAZ圏内の住民避難が完了するまでUPZ圏内は屋内退避にとどめ、避難指示を出さないということである。原発が炉心溶融を起こしPAZ圏内の避難が始まっているときに、窓からそれを眺めながら屋内に留まり続けるのは自家用車を持たない避難弱者以外ありえず、非現実的な対策でしかない。
鹿児島県は避難計画の説明会を行うのであれば、シミュレーション結果もあわせて説明すべきである。
再稼働の条件づくりの作文
実は、全国的には避難計画の策定は必ずしも進んでいない。東海第二原発や浜岡原発では周辺人口が多く、避難計画の策定は 困難とされている。橋本茨城県知事は「UPZにつきましては人口が約94万人、該当する市町村の全人口では106万人と極めて人口が多いことから、県内にあるバスを総動員しても1回に24万人しか搬送できないため、一斉に106万人を避難させるのは不可能であると考えております。」と2012年3月に議会答弁している。
安倍首相は、本年3月28日の参議院本会議で「地域防災計画、避難計画は、地域の状況に精通した自治体が策定するものであり、住民の安全、安心を高めるためにも継続的に改善充実を図っていくべきもの。できないという後ろ向きの発想ではなく、どうすれば地元の理解を得られる、よりよいものにできるかが重要」と答弁している。今後改善充実が図られれば、実効性を伴わない避難計画であってもやむを得ないと布石を打つものであろう。
このような中、川内原発が再稼働一番手と目される理由の1つに、地元で避難計画の策定が完了していることが挙げられている。しかし、その実態はこれまでみてきたとおりの机上の作文でしかない。
泉田新潟県知事は「避難計画は実際には機能しない。国の制度全般を見直さない限り、自治体が有効な避難計画を作るのは不可能だ」と明言している。鹿児島県知事や薩摩川内市長らがこうした問題を理解していないとしたら、能力的に失格である。否、きっと再稼働を優先するために、分かったうえで見ないようにしているのであろう。住民の生命財産を守るという責務を放棄していると断ぜざるを得ない。
このページのTOP
HOME
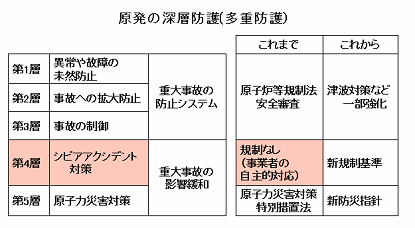 優先審査決定を受けて記者会見した岩切秀雄薩摩川内市長は「日本で一番安心安全な原発と理解したい」と述べている。いくら原発再稼働を公約に掲げて当選した市長とはいえ、原発地元で新規制基準と安心安全が別の問題であることを理解していないのでは、失格である。
優先審査決定を受けて記者会見した岩切秀雄薩摩川内市長は「日本で一番安心安全な原発と理解したい」と述べている。いくら原発再稼働を公約に掲げて当選した市長とはいえ、原発地元で新規制基準と安心安全が別の問題であることを理解していないのでは、失格である。