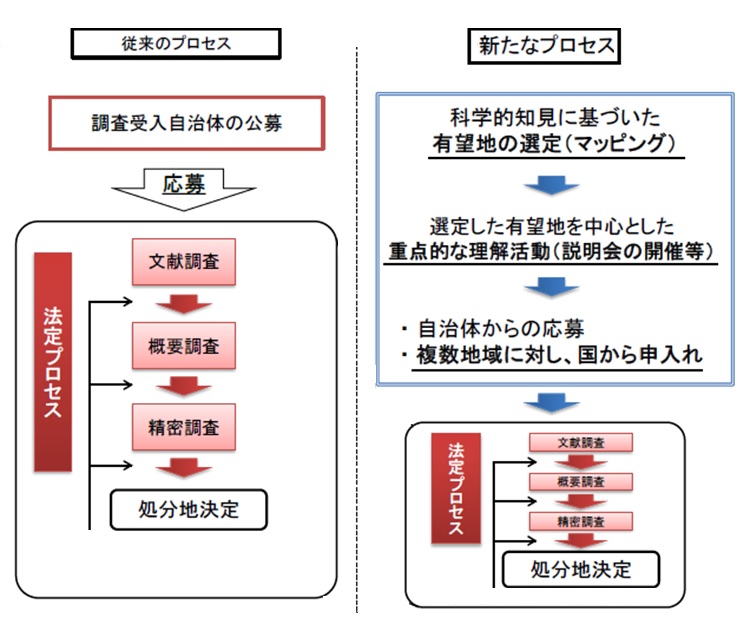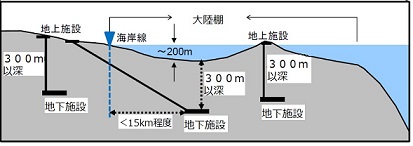総合雑誌アジェンダ48号掲載「再稼動で核のごみを増やし続けてどうするのか」を加筆修正
原発稼働で生じる使用済み核燃料をどうするのか。福島原発事故が起きる前からの根源的な問いです。電力会社の目先の利益のために、将来世代にツケを残すのは倫理的にも許されません。| ① | 高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策の抜本的見直し |
| ② | 科学・技術的能力の限界の認識と科学的自律性の確保 |
| ③ | 暫定保管および総量管理を柱とした政策枠組みの再構築 |
| ④ | 負担の公平性に対する説得力ある政策決定手続きの必要性 |
| ⑤ | 討論の場の設置による多段階合意形成の手続きの必要性 |
| ⑥ | 問題解決には長期的な粘り強い取組みが必要であることへの認識 |